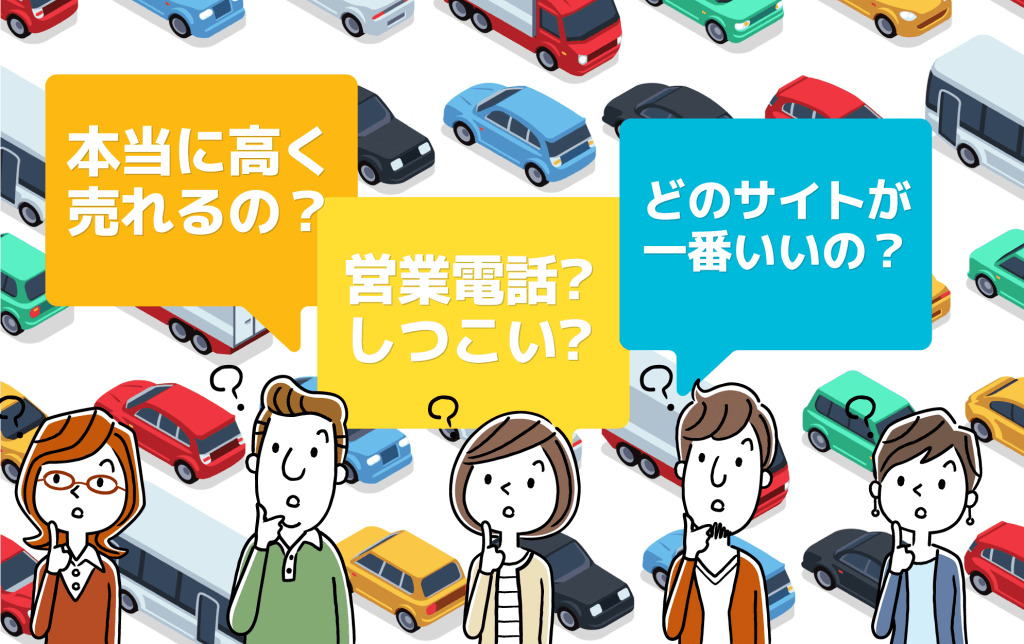コラム | 2021.08.28
世界最高峰ラリーWRCの魅力に迫る!トヨタ ヤリスだけじゃないワールドラリーカーのカッコよさをご紹介
Posted by 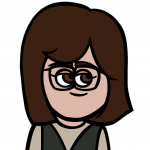
2020年のシリーズ7戦で4勝を挙げたトヨタ ヤリスWRカー。その強さが半端ないことを証明しています。『WRC(世界ラリー選手権)』を始めとするラリーは、日本人にとってあまり馴染みのあるレースとはいえません。サーキットレースとはどのような点が違っているのか、また2021年の『WRC』ではどのような車が出場しているのでしょうか。分かってくると面白いラリーの魅力をご紹介していきます。
以下の文中の買取査定額は、投稿日時点での目安になります。実際の査定額については相場状況や車両の状態によって大きく変動しますので、あくまで参考金額としてご覧ください
ラリーの歴史はWRCの歴史

Art Konovalov / Shutterstock.com
ラリーの歴史を辿ると、中世の騎士たちが領主の元に誰が一番早く到着できるかを競う競技にあるようです。20世紀に入ると馬から車へと継承されていきました。それと同時に公道で行われていた競技は安全面などの理由もあり、サーキットで行われるレースへと変わっていきます。
しかし公道で行われていた自動車競技としても、残っていきそれが現在のラリーです。起源とされるレースは1911年に行われた『ラリー・モンテカルロ』といわれており、名前を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。
当時から参加者たちは、ヨーロッパの各都市を出発し、指定された地点を通過するために、険しい山々を超えてモナコにゴールするというものでした。今でもクラシックラリーとして開催されています。
ところで世界三大ラリーと呼ばれている大会があることはご存じでしょうか。モンテカルロのほかにあと2つ。『ウェールズ・ラリーGB』と『サファリラリー』があります。昔は長時間にわたる長距離走行で優勝を争う大会が多かったようです。
現在『WRC』 が採用しているのは、短距離でタイムアタックを繰り返すスプリント形式。コースや日程をコンパクトにしたものとなっています。欧州や南米では『F1』 に負けない人気を誇っているといえるでしょう。
日本では開催されていなかったため、観戦する機会が少なくあまり盛んではないかもしれません。しかしかつて海外で活躍していた国産メーカーのラリー仕様車が、人気になっていることは周知のことです。ではどのような大会なのかを詳しく見ていきましょう。
WRCラリーを大解剖

Rodrigo Garrido / Shutterstock.com
WRCラリーはスペシャルステージ(通称SS)といわれる交通を遮断した一般道を、市販車をベースにしたWRカーで激走。サーキットレースとは異なり1台ずつ、1~3分間の間をあけてスタートします。
SSはマータック(舗装路)、グラベル(未舗装路)、スノーといったさまざまな道路を使用して行われるため、見ごたえのあるレース展開となる場合が多いものです。その道を3~4日間に15~25本のアタックし、その合計タイムで勝敗が決定。
各地を転々と移動するためSSの開催地から次のSS開催地までは公道を走行することになります。この移動区間のことをリエゾンと呼んでいますが、リエゾンは、一般車両が走行する道路なので、交通ルールを守った走行でなければなりません。
過去には、このリエゾン区間で道路交通法違反を犯したドライバーがいました。その場合、執行猶予時間が設けられますが、決勝当日に執行猶予時間が切れてしまうという非常事態が起こります。
通常ならば、リタイアするだろうと予測されますが、ラリーの最大の特徴は、ドライバーのほかにもう一人コ・ドライバーと呼ばれるナビゲーターが同乗していることを知っている人は多いでしょう。
コ・ドライバーがコースの下見をした際に作る「ペースノート」に従って、次の道路状況をドライバーに知らせながら、運転を行っているのです。もし、交通違反でドライバーが免許停止になった場合などは、コ・ドライバーが運転を行いドライバーが助手席で指示を出して完走したという例もあるようです。
他には車がSSを走行中に大きく破損した場合、リエゾン区間に入る前に整備を受けられれば良いのですが、そのままリエゾンに入ってしまうと、危険な破損車や整備不良と判断され、リタイアに至るというケースも少なくありません。
ラリーウィーク
ラリーは1週間をかけて準備から本番が行わるので、その1週間は「ラリーウィーク」と呼ばれています。どのような1週間をすごしているのでしょうか。
月曜日・火曜日 サービスパークの設営
各チームのメカニックが作業を行う、サーキットのパドックのような場所を設営。ここではメカニックの作業や選手の様子を見ることができる
火曜日・水曜日 コースの下見
スペシャルステージ(SS)では全開走行を行うために、下見走行を行う。コ・ドライバーはペースノートを作成する。
木曜日 シェイクダウン(テスト走行)とセレモニアルスタート
各選手が、競技を開始するセレモニーとしてスタート地点に置かれたポディウム(ゲートの付いた台)に上り、スタートする。
木曜~日曜スペシャルステージ(SS)
走行する本数は異なりますが約15~25本のタイムアタックを行う。
日曜日パワーステージと表彰、記者会見など
パワーステージと呼ばれる上位5位までにはポイントが与えられる。全タイムアタックの合計タイムによって勝敗が決まり、表彰式が行われ幕を閉じる
ポイント
ポイントを与えられるのは、ドライバー、コ・ドライバーを対象にしたものと、マニュファクチャラー(製造者)に与えられるものに分けられています。
車両規則
1997年から車両規則が導入されており、数年ごとに変更を加えられながら進化してきました。現在のところ2017年に車両規則の変更があり、エンジンパフォーマンス、空力性能を向上したWRカーの仕様が認められています。
2022年には新たなレギュレーションとしてハイブリッド車の導入が決定しているようです。パワーユニットについては現行同様に1.6Lの直列4気筒ターボエンジンをベースに、100kWのモーターを組み合わせたものとなっています。
今後は街中を走行する際には100%EVで駆動を行いスペシャルステージ(SS)ではEVのパワーブーストを得て走行することが可能となるようです。
また現在のクラス分けとしてRC1をトップにRC5まで分類されています。それに対して車両グループは下位のカテゴリーになるに従いR4からR1へと数字が小さくなり、分かりにくいと指摘されていました。
今後は最上位クラスから「ラリークラス1」から「ラリークラス5」までに分けられ、以前よりも分かりやすくなっています。
ギャラリーポイント
一般道や林道などを封鎖して行われるラリーには、観客席はあまり多く用意されていません。そのためギャラリースポットとなる場所は、決められているわけではないともいえます。その分、目の前を猛スピードで駆けぬけるラリー車を見ることもできます。
しかしコースオフした車がギャラリーに飛び込んでくることもあり大変危険です。過去には死亡、負傷事故につながったこともあるため、観戦するポイントも危険を避ける場所を選ぶ必要があるでしょう。。
タイヤ
以前はタイヤに制限は加えられていませんでしたが、現在のレギュレーションではトレッドパターンなども規制があります。トレッドはターマック、グラベルで1種類、コンパウンドは2種類まで。しかし『モンテカルロ』では、路面の変化が激しいため、4種類まで認められているようです。
通常ターマックでは車高を下げ、大径の18インチホイールを装着します。それに対して路面の変化が激しいグラベルではサスペンションの保護などの為、車高を上げて15インチホイールを装着。タイヤのセッティングはタイムに大きな影響を与える存在でもあるようです。
レギュレーション
2018年度のレギュレーションは以下の通りとなっています。
エンジン…1.6L直噴ターボ
最低重量…1,175㎏
最小全長…3,900mm
規定最大全幅…1,875mm
2021年度のレギュレーション変更点は、タイヤのワンメイク化によって『ピレリ』が導入されたことが挙げられます。
日本勢の華々しい活躍の過去とトヨタ ヤリス

Rodrigo Garrido / Shutterstock.com
過去をさかのぼると、ラリー参戦を果たしていた国産メーカーは、驚くことにホンダを除く日本の主要メーカーばかりです。
日産
『WRC』が開催される以前から参戦を果たしており、『サファリラリー』で圧倒的な強さを誇っています。1979年~1983年には史上初となる4連覇を果たしたこともありました。しかし1991年~1992年のパルサー GTI-Rを最後に撤退。ダットサン時代と合わせると通算9勝を挙げていることになります。
三菱
1973年から参戦を開始。『サファリラリー』を制したのはランサーでした。1989年~1992年にはギャランで5勝を挙げ、1993年にはランサー エボリューションがデビュー。1996年~1999年までトミ・マキネンによる4連勝は記憶に残っているのではないでしょうか。
2005年には経営悪化を理由に休止が発表され、以来事実上の撤退となっています。
マツダ
1981年にサバンナRX-7で参戦を開始。最高3位を収める結果となりました。その後ファミリアに切り替えられ『ニュージーランド・ラリー』で3回の優勝を経験しています。しかし1992年に業績不振により撤退を表明しました。
スバル
レオーネで初優勝を上げたのは1980年のこと。以降1995年にはレガシィでマニュファクチャラーズ・タイトル3連覇を果たしています。また2003年から2007年まで5年連続のドライバーズタイトルを獲得するなど、大活躍を見せました。しかし2008年に経済的問題と、当初の目的達成を理由に撤退を決めています。
スズキ
2002年にはイグニスとスイフトでドライバーズタイトルを3度獲得し、通算勝利数はシトロエンに次ぐ第2位の24勝を挙げました。しかし2007年からSX4での参戦でトラブルなどが多く完走もままならない状態になります。
2008年には改良を重ね、完走は果たすものの結果に結びつくことが少なくなっていきました。同年にはリーマンショックのあおりを受け、撤退を表明することになってしまいました。
ダイハツ
1979年-1981年の『モンテカルロ』に、シャレードでスポット参戦すると、クラス優勝を勝ち取ります。1982年からは『サファリラリー』に参戦しクラス6度の優勝を果たすことに成功。排気量が1Lも大きい車を相手に、5-7位に食い込む大健闘を見せます。
いすゞ
乗用車を製造していた時代には『WRC』 にスポット参戦しアスカやジェミニを使用して、1983年には優勝を経験。現在はトラックメーカーとして活躍しているメーカーとは思えない活躍ぶりでした。
トヨタ
現在も国産メーカーとしてラリーに参戦しているのは、トヨタだけという寂しい現実となっています。トヨタがラリーに初出場したのは1957年のことでした。その後は『サファリラリー』3連覇など輝かしい記録を樹立。
1993年には日本メーカー初となる『WRC』 マニュファクチャラーズ・タイトルを獲得するに至っています。トヨタが『WRC』 に挑み続ける理由は、「もっといいクルマづくり」です。
ラリーで挑む様々な道路状況はトヨタにとって鍛錬の場所であり、市販車開発にフィードバックすることができる生きた経験になるからにほかなりません。その結果としてヤリスWRCの結果がGRヤリスの結果に結びついているといえるのではないでしょうか。
ヤリスWRCとは
ラリー競技を戦うトップカテゴリーマシンとして仕上げられたのがヤリスWRCです。レギュレーション規定通りとなっていますが、最高出力380ps以上を発揮。また最大トルクは425Nm以上となっています。
6速のセミオートマチック・ギアボックスとアクティブ・センターデファレンシャルを持つフルタイム4WDを搭載。効率よく4輪に伝えることを可能にしています。またデザインにはオーバーフェンダーを採用して車幅を拡大。
大型のリヤウイングといった専用のエアロパーツを装着して安定性能を向上しています。2021年度は、エアロダイナミクス、サスペンションといったパーツにアップデートが予定されているようです。エクステリアにはGRを意識したレッドとブラックを基調にしたインパクトのあるデザインとなりました。
ラリージャパン
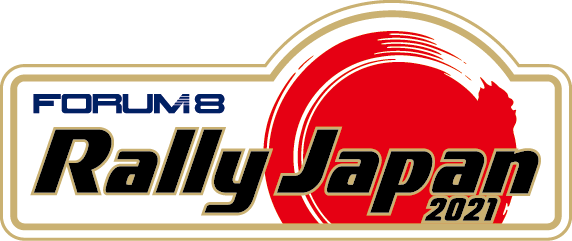
https://rally-japan.jp
ラリージャパンは、『FIA』の管轄する『WRC』日本ラウンドのことです。2004年に初開催されたのは北海道でした。2008年と2010年にも北海道で開催されています。2017年にトヨタが『WRC』 に復帰したことで関心が集まってきていたようです。
2020年には愛知県、岐阜県で開催が予定されていましたが、新型コロナウイルスの影響を受け中止されました。2021年度も引き続き、年間最終戦に設定されており、11月11日に愛知県での開催が予定されています。状況に応じて変更はあると思われますが、ぜひ実現することに期待したいものです。
2021年エントリー注目車
現在第8選までを終え、残すところ4戦となっています。レース結果を見ると『トヨタ GAZOOレーシングWRT』の強さが圧倒的ですが、そんななかで注目される車両は、どこの国のどのような車両があるかをご紹介しておきましょう。
ヒュンダイ シェルモービスWRT

Rodrigo Garrido / Shutterstock.com
WRCにあまり興味のない人にとっては、意外かもしれませんが、韓国の自動車メーカー『ヒュンダイ』のi20クーペWRCです。マニュファクチャラーズ・チャンピオンシップの順位では現在トヨタに次ぐ第2位に位置しており、活躍が期待されます。
Mスポーツ フォードWRT

Fabrizio Buraglio / Shutterstock.com
イギリスに本拠地を置くモータースポーツ関連企業で、マニュファクチャラーとして『WRC』 に参戦。採用されているマシンはフォード フィェスタWRCです。若手ドライバーの才能で今期の走りに期待されるチームといいえるでしょう。
まとめ

Nacho Mateo / Shutterstock.com
市販車両に極めて近い車を使用して、強烈な加速で砂漠や雪道などさまざまな公道を疾走する姿は、サーキットとは異なる魅力があります。恐ろしく狭い道や岩壁、崖の迫る公道では一つのミスが許されない極限状況をとてつもないテクニックで走行する様は見るものを惹きつけてやみません。
ラリーを知らなくても見ているだけで楽しいものですが、少しでも知識を持って観戦すると今までとは違う見方ができるのではないでしょうか。ジャパンラリーが開催されることを期待しつつ、観戦経験がないという人は、一度観戦してみてはいかがでしょうか。