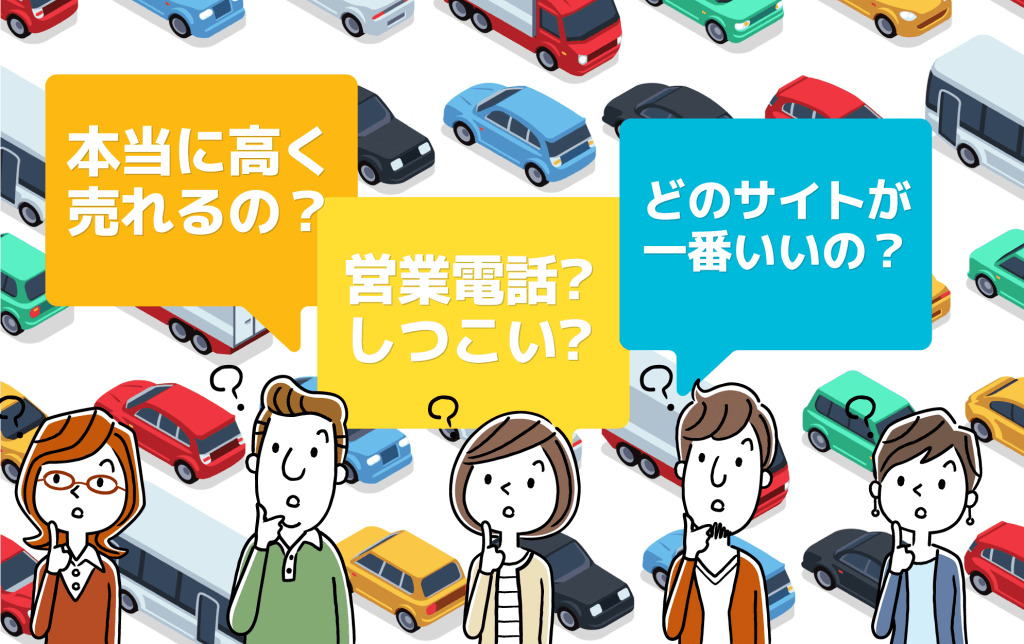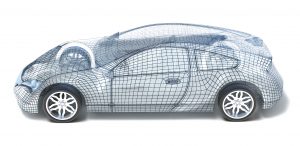カスタム・アフターパーツ | 2021.05.11
最近良く見る「流れるウィンカー」はなぜ増えている?自分で取り付けるには?
Posted by 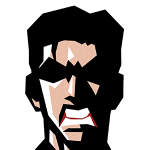
10年ほど前から少しずつ増え始め、最近では新型車への採用やアフターパーツとしての新製品も増えている「シーケンシャルウィンカー」。「流れるウィンカー」などとも言われますが、市場に増えている理由と、DIY装着の注意点などを紹介します。
以下の文中の買取査定額は、投稿日時点での目安になります。実際の査定額については相場状況や車両の状態によって大きく変動しますので、あくまで参考金額としてご覧ください
実は昔からあった「流れるウィンカー」

Felix Mizioznikov / Shutterstock.com
割と最近の流行に見える「流れるウィンカー」。国土交通省の正式用語では「連鎖式点灯方向指示器」、一般的には「シーケンシャルウィンカー」とも呼ばれますが、2014年の保安基準改正で日本でも正式に認可されたことにより、広く一般的になった印象です。
しかし実際には、1960年代からアメリカでマスタングなどが採用、まだウィンカーの点灯色が橙(オレンジ色)と決まっておらず、赤いテールランプをウィンカーと併用していた時代の日本でも、初代ローレル(1968年発売)などで採用されていました。
初期の流れるウィンカーは、単なるブレーキランプの点灯と区別し、ウィンカーとしての視認性を向上させる意味合いもあってか、複数並んだ尾灯を内側から外側へ順番に点灯させていき、全て点灯すると消灯、また内側から点灯という繰り返しで「流れるウィンカー」を表現していましたが、それは現在のLED式でも変わりません。
ただし、それらはあくまで純正状態で国交省(昔から運輸省)から認可されただけで、改造して「流れるウィンカー」にすることは認められていませんでした。
しかし、デザイン上のアクセントとしては視認性以上に効果が高いアイテムであったため、2006年の保安基準改正による規制強化までは、主にトラックなどで「流れるウィンカー」は公道上で普通に見かけたのも、また事実です。
したがって、ご年配の世代でなくても、「流れるウィンカーなんて昔からあったよね?」「むしろデコトラを思い出す」という人が多いと思いますが、2014年の保安基準改正以降は一気に増えてきたのはなぜでしょう?
デザインの画一化が産んだ?「流れるウィンカー」の流行
トラックはともかく、乗用車ではあまり一般的と言えなかった「流れるウィンカー」に復権の兆しが来たのは、2009年(日本では2010年12月)、アウディ・A8にシーケンシャルウィンカーが採用されて以降のことです。
一応は「視認性向上のため」と、もっともな理由はついているものの、現実にはデザイン上のアクセントとしての役割が大きいシーケンシャルウィンカーは、まだコスト高とはいえ小型でも明るく光るLEDランプの登場で、一部高級車から採用され始めます。
日本ではまだ保安基準の問題があったものの、ヨーロッパ製の一部高級車といえば日本はお得意のひとつですし、高級車を輸出している国産メーカーにとっても国内外でつくり分けずに済むというメリットがあるため、例によって非関税障壁撤廃という圧力を内外から受けて、2014年に晴れて「流れるウィンカー」は解禁となりました。
それからしばらくは高級車御用達の標準、またはメーカーオプションパーツとして採用されてきましたが、最近ではコンパクトSUVのヤリスクロスや、軽乗用車のN-BOXやタントなどにも採用が進み、だいぶ一般化してきた傾向があります。
それどころか、解禁の主な原因となったはずの輸入車より国産車メーカーの方が積極的に採用しているほどで、アフターパーツとしても汎用品が多数登場し、今やDIYで簡単取り付けを宣伝する製品もあるほどです。
原因としては、歩行者衝突時保護など衝突安全基準の強化、環境性能向上のため徹底した空力性能の向上、さらに流行したデザインしか売れなくなるなど「クルマのカタチ」の縛りが大きくなり、各社とも同ジャンルならほとんど同じような、ちょっとデザイン違い程度の車しかつくることができなくなり、少しでも個性を出そうと悪戦苦闘しているためかもしれません。
もちろんメーカーだけでなく、ユーザーも「他の同じ(ような)車より、ちょっと個性を出したい、カッコよくしたい」という願望があるため、設定のない車種でもアフターパーツがあれば飛びつく、というわけです。
DIYで簡単取り付け!ではありますが…
最近の流行はただの「流れるウィンカー」から一歩進んでおり、「通常はデイライトとして常時白色点灯、ウィンカー作動時はデイライトを消灯し、内側から外側へ橙色の流れるウィンカーとして作動」という「ダブルファンクションウィンカー」へと移っています。
アフターパーツメーカーから「DIYで簡単取り付け!」という製品もこのダブルファンクション式が登場していますが、近年多い「横に切れ長のLEDヘッドライト&ウィンカー」というデザインの車であれば、汎用品でも容易に取り付け可能です。
注意しなければいけないのは、現在の保安基準における以下の要件を満たすこと。
・光源の各LEDは、点灯後すべてのLEDが点灯するまで作動し続ける。
・作動後、全LEDが同時に消灯。
・LEDは垂直(縦)方向に反復して点灯しない。
・LEDは最内縁(内側)から最外縁(外側)に向かって点灯、または中心から放射状に広がって均一的かつ連続的に点灯。
・照明部に外接する長方形で、長辺部が進行方向に対し垂直な面に平行で、長短の比率が1.7:1以上。
最初の2つはそれを満たした商品を買えばよいだけですが、後付けの場合、垂直や極端に斜め、あるいは短すぎる「流れるウィンカー」は違法になります(円形ヘッドランプの中心から外側へもアリに見えますが、現状ハッキリしません)。
いろいろな解釈はあると思いますが、たとえば警察の取り締まりでもグレーゾーンに対して「これはダメだ」と解釈して譲らない警官がいてもおかしくありませんし、誰が見ても文句のつけようがない「純正の灯火類に沿って装着」、あるいは「純正ウィンカーとの交換」が間違いないでしょう。
また、このあたりは料理サイトの「簡単にできちゃうレシピ」と共通なのですが、簡単取り付けと言いつつ検電テスターや圧着端子、工具類の準備が必要だったり、車両のアクセサリー線を探さなければいけないなど、「多少の心得がないと、説明書を見ても何がなんだかわからない」というのはありがちです。
DIYで簡単取り付け!と言ってもウィンカーは安全に関わる重要部品であり、一歩間違えれば変なところのヒューズを飛ばしたり壊す原因にもなりかねないため、作業する場合は、多少なりとも知識や経験がある人と一緒に、あるいは最初からショップで施行を依頼することをオススメします。