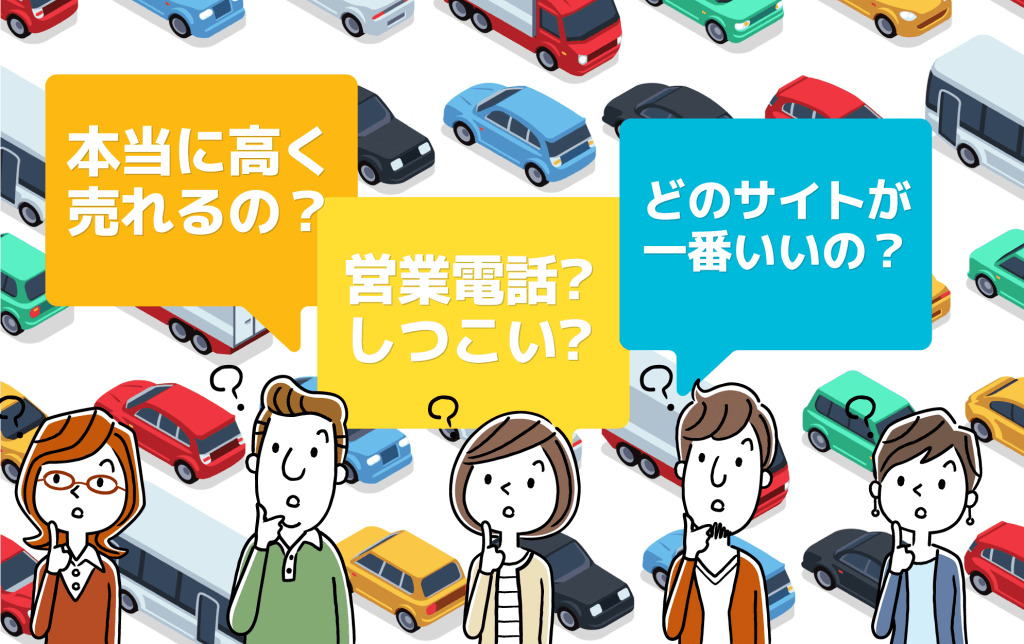コラム | 2021.05.29
頭文字Dに登場する庄司慎吾のひとことでホンダが動いた?まことしやかな都市伝説、S2000の誕生秘話に迫る!
Posted by 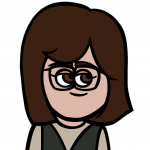
1995年に『講談社のヤングマガジン』で連載が開始された不朽の名作『頭文字D』。アニメではスキール音にまでこだわり、リアルなバトルシーンの再現は、車好きの心を躍らせたものです。連載期間18年の中、記憶に残るバトルといえば、「ガムテープデスマッチ」もそのひとつではないでしょうか。S2000を語るうえでどうしても切り離せない『頭文字D』のサブキャラクターのひとり「妙義ナイトキッズ」の庄司慎吾のひとことと、S2000の開発秘話を検証していきましょう。
以下の文中の買取査定額は、投稿日時点での目安になります。実際の査定額については相場状況や車両の状態によって大きく変動しますので、あくまで参考金額としてご覧ください
頭文字Dに登場する妙義ナイトキッズの庄司慎吾とは

Rakhmat Darmawan / Shutterstock.com
「妙義ナイトキッズ」のNo2を名乗る庄司慎吾は、ホンダ シビックEG6を乗りこなす腕前の持ち主。「秋名スピードスターズ」の池谷とのバトルで見事な左足ブレーキを披露しており、口先だけではないことが証明されます。
主人公の藤原拓海とのバトルまでは、ちょっと憎らしい人格。しかしバトルで事故に遭い池谷たちが助けに来てくれたことに感謝するあたりから、キャラクターに変化が見られるようになってきます。
庄司慎吾が乗っているシビック EG6は1991年に誕生。「スポーツシビック」と呼ばれ、90年代のテンロクスポーツを代表する一台といえるでしょう。ホンダを代表するホットハッチで、実用的かつスポーツ性能を秘めたVTECはパワフルそのもの。若い世代を中心に人気の高い車でした。
そんなEG6を操る庄司慎吾は、作中で最高出力を185psにまで高めたチューニングを施しています。そこでAE86の藤原拓海に挑んだバトル、これこそが「ガムテープデスマッチ」です。右手をガムテープでステアリングに固定するというもの。つまりステアリングを切ることが難しく、180°程度しか曲げることのできません。
つまり、ステアリングでコーナーを曲がることは不可能。ステアリングはドリフトのきっかけづくりにしかならず、コーナー走行中に後輪が滑っている際に制御するために逆方向へステアリングを切るカウンターステアができないのです。
それは軌道の修正が非常に難しく、遠心力に負けて車両が外側に膨らんでしまうアンダーステアに陥る可能性が高くなります。その際はサイドブレーキでリアを滑らせるように調整することで対応できるかもしれません。
しかし反対に車が内側に切れ込むオーバーステアに対しては、FF車であればアクセルを踏み込むことで体制を保つことができる確率は高くなるでしょう。ですがFR車ではなすすべがないということになります。
ガムタープデスマッチは圧倒的にFR車に不利な条件なのです。しかし藤原拓海は見事にFRの弱点を克服します。勝敗に敗れ、チームの笑いものになることを恐れた庄司慎吾は、ダブルクラッシュを試みますが、藤原拓海にかわされてひとりでクラッシュ。
幸い怪我は免れますが車は損傷が激しく、涙ぐみながらEG6を見つめています。庄司慎吾というキャラは憎まれ役なのかもしれませんが、藤原拓海が進化するうえで重要な役割を果たしているともいえるでしょう。
その後の話の展開から、シルエイティに乗る佐藤真子のナビ兼メカニックを担当している沙雪と幼馴染であることが判明。また犬猿の仲だった妙義ナイトキッズの中里毅とも仲良くなるなど、かなりのキャラ変ぶりを見せており、憎み切れないバイプレーヤーになっていきます。
そんな庄司慎吾が、語った言葉。それが「俺だってホンダがFR作ってくりゃ、乗り換えるよ」です。FRキラーの庄司慎吾は、FF信者かと思われていましたが、実はホンダ信者であったことが判明した瞬間でした。
さてこの言葉、連載が行われていた1996年当時に発せられています。S2000が誕生したのは1998年のこと。つまり庄司慎吾の嘆きから、ホンダがS2000を作ったのではないかという都市伝説がささやかれているのです。
これはもう『頭文字D』ファンの間では有名なものですが、ホンダがS2000を開発したのはどういった経緯があったのか、どんな車だったのかを改めて振り返ってみましょう。
ホンダSシリーズの誇り

Simlinger / Shutterstock.com
Sシリーズの歴史を紐解くと1963年にまで遡ります。本格的なライトスポーツとして誕生したS500は、販売期間わずか1年でした。しかし翌年S600が登場することに。2シーターのスタイルはそのままにパワーアップしたエンジン性能で、ホンダの技術力を見せつけました。
モータースポーツへの進出を果たし、2輪のみならず4輪でもホンダの名を馳せることになります。その後S800が1966年に発売。スタイリングに大きな変更はなく、ライトスポーツの性能はそのまま引き継がれました。しかし1970年に生産を終了。
惜しまれながらもその役目を終えることになりました。そして29年の時を経てSシリーズが復活。この車こそがS2000でした。ホンダが初めて作ったスポーツカーであり、シリーズの開発を提案したのは本田宗一郎さんです。どの車もSという名前の誇りを感じられる名車だったといえるでしょう。
開発者たちの熱い思い

Jevanto Productions / Shutterstock.com
そんなS2000は、1995年に行われた『東京モーターショー』に出展したコンセプトカー「ホンダ・SSM」の反響を受けて市販化が本格的となっていきます。開発に携わったのはNSXの開発を手掛けた上原繁さんを始めとする技術者の面々でした。
S2000を手にすることでしか得られない魅力と価値の思いから開発が始まったと開発責任者の乙部豊さんは振り返っています。テスト用のエンジンをいくつ潰したか分からないほど試行錯誤を繰り返し、燃焼室の温度が上昇し、ピストンが溶融することも想定内だったようです。
「また溶けた」を何度も何度も繰り返し、技術を鍛え、決してあきらめることなく取り組んだ結果、誕生したエンジンでした。出力だけにとらわれることなくレスポンスも徹底的に追及。トランスミッションの軽量化、ドライブシャフトの高剛性化にもこだわっています。
横滑りなど挙動の乱れを抑えるために装着された「VSA」によって高い次元で走行性能を発揮させました。空力とサスペンション性能をトータルにセッティングすることで、ワインディングを気持ちよく走ることのできるセッティングを目指しています。
その走りは、サーキットのラップタイムを削るために開発されている「TYPE R」とは少し方向性が異なっており、軽快なハンドリング性能で気持ちの良い走りを実現させるためのものです。
TYPE Sの開発では、空力にこだわり抜いたデザインが採用されています。例えばリアスポイラーに至っては、車体を浮き上がらせるリフト量を抑えてドラッグと呼ばれる空気抵抗を増やさない。加えてオープン時とクローズ時の空力特性を最小限にとどめるという難題をクリアした結果、これまでの常識を覆すことに成功。
一体成型では難しいとされていた薄さ6mmの後縁や、長い垂直板を使用したブロー成型を実現しました。フロントスポイラーの下面も可能な限り下げることに成功。また斜め前方に張り出した面も、リフト量を低減させるために重要なものです。
サイド部分の垂直面を大きく取ることで、タイヤ後方で発生するドラッグと呼ばれる渦を抑えることができるため、斜め前に張り出たスポイラーの形状が重要となります。見た目のデザイン性だけではなく徹底的に開発を行った結果として、高い次元で両立することが可能になっているといえるでしょう。
もう一つには前後最適なリフトバランスが挙げられます。空力の前後バランスは、高速域でのハンドリング性能への影響を小さくするためのものです。前後重量バランス50:50に成功し、ドラッグを増やすことなく全体で約70%の揚力を低減するという空力デザインが完成しました。
結果的には9年間で1代限りという形によって生産が終了したS2000ですが、これほどの高出力エンジンの量産は、もう二度と開発されることはないだろうと乙部さんも語っています。その凄い性能はどのようなものだったのでしょうか。
庄司慎吾が手に入れられなかったS2000のスゴイ特徴

Max Anuchkin / Shutterstock.com
実際のところ、S2000はホンダ技研工業創立50周年の記念モデルとして誕生しています。1998年に『ツインリンクもてぎ』で行われた記念イベント「ありがとうフェスタinもてぎ」でホンダの歴代社長がパレードに使用する車としてお披露目されました。
Sシリーズの生産が終了してから29年の年月が経った中、FRスポーツカーが存在していなかったホンダにとって、兄弟車や派生車種も存在していませんでした。通常なら生産台数の多い車のパーツを流用し価格を抑えるという方式が採用されるもの。
しかしホンダは全てのパーツをS2000専用パーツとして一から開発を行っています。ですがそれゆえに技術者たちは、リアルスポーツカーのあるべき姿を追求することができた車でもあり、さまざまな点において贅を尽くした仕上がりになったといえるでしょう。
軽量小型のオープンカーの弱点でもあるフレームには、「ハイXボーンフレーム構造」で高い剛性を確保。当時は希少だった6速マニュアルトランスミッションも自社開発の専用パーツです。
またフロントミドシップの50:50の重量バランスの実現。エンジンにおいてはF1にも匹敵するショートストローク型を採用。レブリミッターは9,000回転に達しています。最高出力250psを8,300回転で発生させることができるという高出力エンジンです。
マイナーチェンジ後に登場した「Type V」では市販車両として、世界初となる「可変ギアレシオステアリング」が採用されました。これによって車速と舵角に応じてステアリングのギア比を変更できるという優れものです。
高速走行では穏やかなステアリング性能ですが、ひとたびタイトなコースを走行という際には、クイックな応答性が期待できるホンダならではのマニアックなエンジンといえるでしょう。
専用パーツをふんだんに使用し、これ以上のエンジンは今後作ることはできないとホンダの技術者も語っているS2000。ホンダ党の庄司慎吾はFRのS2000が登場で、乗り換えることができたのでしょうか。
S2000販売後に掲載された番外編の「センチメンタルホワイト」の中で、幼馴染の沙雪にS2000を買うのかと尋ねられる場面があります。その答えは貧乏でお金がないということで、手に入れられずじまいだったようです。
まとめ

Stasiuk / Shutterstock.com
庄司慎吾のひとことでホンダがFRを作ったわけではなく、『ホンダ技研工業』誕生50年の記念モデルとして誕生したS2000。『頭文字D』ファンとしては、少し残念な気もしますが、都市伝説は、そのままにしておくのもアリなのではないでしょうか。
専用パーツで登場した軽量リアルスポーツカーは、驚くほどの性能を秘めた一台でした。またいつか車好きの心を掻き立てるFRをホンダが作ってくれることに期待したいものです。
↓ホンダ車のおすすめ記事3選↓
NAでリッターあたり100馬力超!ホンダVTEC搭載の名車4選