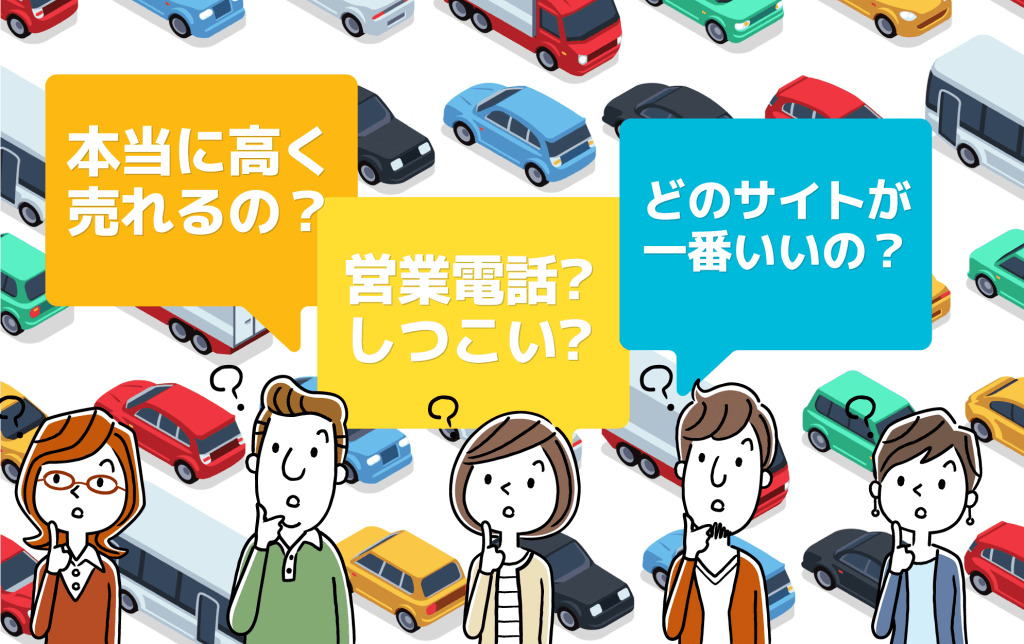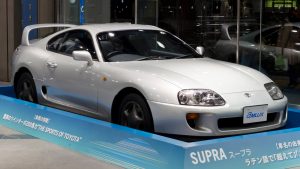カスタム・アフターパーツ | 2021.05.11
「Sタイヤ」とは?普通のタイヤとどのように違う?
Posted by 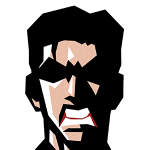
スポーツ派のクルマ好きにとっては、ちょっとした特別なアイテム、通称「Sタイヤ」。 公道走行も可能とはいえ、耐摩耗性や静粛性より、とにかくグリップ優先、構造も大きく異なるレーシングタイヤに準じた「セミスリックタイヤ」がその正体です。 一般的なスポーツタイヤと何が違うのか、どのようなシチュエーションで有効なのかを紹介します。
以下の文中の買取査定額は、投稿日時点での目安になります。実際の査定額については相場状況や車両の状態によって大きく変動しますので、あくまで参考金額としてご覧ください
SUMMARY
公道走行も可能なレーシングセミスリックタイヤ、通称「Sタイヤ」
F1など、通常は全く溝のない「スリックタイヤ」が使われることの多いレーシングタイヤの世界においても、安全性向上のため速度低下を目的としたり、路面上に水たまりができ、ハイドロプレーニング現象を防ぐため排水性能が求められる場合などには、溝のあるタイヤが用いられることがあります。
特に後者は「レインタイヤ」として知られますが、路面とタイヤの間に水が入って浮かないよう市販タイヤに準じた排水性能を持ちつつ、レーシングスピードに耐えうる強固な構造を持っており、レース専用タイヤ以外に公道走行も可能なスペックがあるということで、一般に市販されているものもあり(スリックタイヤは一般市販禁止)、それが「Sタイヤ」です。
SタイヤのSはセミスリック、またはセミレーシングのSというわけで、あくまで公道である程度のスポーツ性能と同時に、耐摩耗性やロードノイズ低減による快適性、そして何よりコストも重視した、Sタイヤに対して「スポーツラジアル」とも呼ばれる一般スポーツタイヤとは、また違った次元のタイヤとなっています。
グリップ最重視のコンパウンドを採用し、ロードノイズは無視!
Sタイヤは公道も走ることができますが、実際に公道で使ってみると「ゴロゴロゴロ」と、特殊な溝などが掘られて、あえて音が出るようにつくってある路面を常に走っているような、ロードノイズがひたすら耳につきます。
履いてすぐは、とにかくこのロードノイズが「いかにもレーシングタイヤ」という気がして有頂天になるものですが、次第にただうるさいだけに感じるようになり、そしてやがては慣れて何とも思わなくなる、Sタイヤを経験したユーザーであればわかる話です。
これはSタイヤに使われているタイヤゴム表面の「コンパウンド」と呼ばれる素材や、タイヤ形状も含めて吸音性など一切考慮されていないためで、とにかくグリップ一辺倒で考慮しているためです。
コンパウンドには大きく分けてソフト、ミディアム、ハードと3種類あり(実際にはもっと細分化されています)、高温になる猛暑下のサーキット走行や、超高速コースなどタイヤが超高温になるケース、耐久レースのようにグリップより対摩耗性を重視してタイヤ交換回数を減らしたい場合などは、ハードコンパウンドを使用します。
横Gばかりが続くジムカーナ走行や、スターティンググリッドを決めるレース予選など、短距離だけでもグリップ超重視という場合は、ソフトコンパウンドを使い、前後グリップの調整、ソフトコンパウンド以上ハードコンパウンド未満な性能が求められる場合は、ミディアムコンパウンド、といった具合です。
超高速や横Gに耐える強固な構造
単にグリップが強力なコンパウンドを使っただけのタイヤであれば、普通のタイヤにも存在し、まさにSタイヤのコンパウンド使用を売りにして、Sタイヤ禁止の競技会では使用不可とされているスポーツラジアルさえありますが、Sタイヤはコンパウンドだけが特殊なわけではありません。
構造的にも一般的なタイヤより余程強固につくられており、横Gがかかった際にスポーツラジアルであれば、歪んでホイールが接地しそうなシチュエーションでも、Sタイヤは平然とタイヤとしての形状を保っています。
それゆえ、普通のタイヤではありえない0.6~0.9kpa程度の低い空気圧でもスポーツ走行が可能で、規則によりタイヤ幅が規制されている場合など、抵抗増加をしのんでもコーナリング性能を高めるべく、あえて低圧タイヤを使用する場合もあるほどです。
また、剛性の高さはグリップ回復スピードにも影響しており、例えば強烈なアンダーステアや激しいブレーキングで一時的にタイヤがグリップを失った際、一般的なスポーツラジアルであれば、回復が遅れてクラッシュへつながるようなシチュエーションでも、Sタイヤはグリップ回復が速く、ドライビングミスを最小限で取り返すとともに、安全性の高さにも直結しています。
雨や寒い日のSタイヤはスポーツラジアルへ劣るのか?
よく、漫画などでSタイヤを装着した車が公道バトルへ登場すると、「温度が上がるまでに勝負をつければ、(Sタイヤ装着車から)逃げ切れる」という表現を目にしますが、レースなどでタイヤの温度を上げるため、ウォーミングアップで蛇行させる場面からの影響でしょう。
実際は、舗装状況がよほど良好で平滑なレース用特殊舗装で、ハードコンパウンドのタイヤを使用した場合であればありえますし、真冬に舗装がまだ真新しい道路を走る時であれば、そういうこともあるかと思いますが、そもそもレース用特殊舗装に比べればザラザラした公道をそれなりの距離走るだけで、Sタイヤはそのグリップ力による抵抗で、十分に温まります。
従って、真冬に冷え切った状態から、スタート直後に全開コーナリングでも行わない限りはSタイヤのグリップが当然のように勝り、レースでは、レインタイヤとしてスリックタイヤに代わって使われるケースがあることからも、ウェット路面であればスポーツラジアルの方が勝るというシチュエーションはまずありえません。
同じドライバーが同じ条件で同じ車を走らせる限り、ほとんどのシチュエーションではSタイヤを履けばタイムアップするのが道理です。
ただし、どうにもならないのが雪上や凍結路面で、雪上であれば、雪や水による抵抗もあるため、ドリフト走行もできますが、凍結路面の場合、スタッドレスタイヤ以外では不足する吸水性能や排水性能が、Sタイヤでは不足どころではないため「まっすぐ走ることができれば上等、曲がったり止まったりは期待するだけ無理」であり、ヘタをすると停車していても風で流されます。
とにかくSタイヤであれば良いのか?車がもたないこともアリ
ならば、速く走ろうと思えばどんな車でもSタイヤを履けば良いのか、といえば然にあらずで、グリップがものすごいタイヤというのは裏を返せば「本来であればホイルスピンなどで逃げる力が、逃げない」ため、車の中でも駆動系に対するストレスは非常に高まります。
すなわち、ミッションやトランスファー、デフなどが弱い車は、Sタイヤばかり履いて走っているとすぐ壊れ、クラッチディスクはすぐ剥離したり、亀裂が入っていくらも持ちません。
グリップ回復が早いため、意図的にタイヤを滑らせるドリフト走行やサイドブレーキを使ったスピンターンでも、グリップ回復した瞬間にドライブシャフトがちぎれたり、FF車ではドライブシャフトのアウター部ベアリング破損による走行不能トラブルも多発します。
時代が進んでコンパクトカーや軽自動車で車高が高く、トップヘビー気味な車が増えてくると、横Gへの逃げがないばかりに横転クラッシュも多発するようになりました。
筆者も2000年代にジムカーナドライバーだった頃には、ミッションやクラッチを壊したことが1年に何度もありましたし、某コンパクトカーで一度転倒を経験してからは、むしろ前後片輪が浮いた瞬間にカウンターステアを当てる(横Gをそらす)のが上手くなったくらいです。
それでも壊れさえせずゴールできれば速く、横転くらいであればダートトライアルやラリーのドライバーから「前転じゃなければ転倒と言わないぞ!」と言われるくらいドライバーや車両へのダメージは少ないため、何だかんだで、皆Sタイヤを履いて走っていましたが、今思えば何ともスパルタンな時代でした。
Sタイヤはすぐ摩耗する?
耐摩耗性を犠牲にしてグリップ力を確保したSタイヤは、確かに一般的なスポーツラジアルと比べて寿命は短い傾向にあり、タイヤの負担が大きいハイパワー車や、重量級の車ではそれこそあっという間に摩耗してしまうため、公道で使用するにしても「もうタイムを出すタイヤとしては使えないため、最後に履きつぶす」くらいです。
しかし、コンパクトカーや軽自動車の中でも特に軽量級でアンダーパワーな車の場合、タイヤの負担がそもそも少ないため、スポーツ走行以外では、むしろエコタイヤ以上に減らない場合さえあります。
ただし、あまりアンダーパワーで軽い車、たとえば車重600kg以下で最高出力も30馬力程度な車(筆者が今乗っている車がまさにそうですが)の場合、Sタイヤの場合、構造が強固すぎて重量増加によるデメリットが目立つ上、強烈なグリップなど全く必要としないため、「タイヤの形をした何か」を履いている以上の意味はないかもしれません。
なお、Sタイヤ以上に寿命が短いと言われるのがラリースタッドレスで、雪上では抜群の走行性能を発揮するものの、舗装路で全開走行すると消しゴムのように減る、と言われています。
現在はSタイヤ禁止のレースや競技が増え、スポーツラジアルとの境目も曖昧
走行性能を追求するのであれば、良いことづくめに思えるSタイヤですが、ちょっと摩耗するともう新品時の性能を発揮できない「賞味期限の短さ」や、当然ながら一般的なスポーツラジアルより高価なこともあり、モータースポーツを低コストで楽しもう、というコンセプトにはそぐわないと、入門者向けのレースや競技会では禁止されることが増えました。
一時は国産タイヤメーカー各社の間で激しい開発競争が行われ、毎年のように新モデルや新コンパウンドが登場していたSタイヤも、市場縮小で今はすっかり新製品の話題が少なくなり、同じモデルを少々改良した程度でずっと販売していることも多くなっています。
新しいSタイヤといえば、ブリジストンが2010年代に入ってRE11Sを発売したのが最後で、横浜のADVAN A050も、ダンロップのディレッツァ03Gも2000年代に発売したSタイヤを改良しつつ継続しており、ちょっとさみしい状況になりました。
しかし、「Sタイヤ禁止というのであれば、スポーツラジアルにSタイヤ並の性能をもたせたら良いのでは?」とは誰もが思うものです。
「これのどこがスポーツラジアルなんだ?」と言わんばかりのコンパウンドやタイヤパターンがいかにもモータースポーツ向けな、「でもSタイヤではない名目」のタイヤが登場したり、海外製のタイヤで最初からほとんど溝がない「スリックタイヤも同然のタイヤ」で競技会に出場するドライバーが出ては、直後に規則改正で禁止されたりのイタチごっこの状況です。
「Sタイヤとギリギリ呼ばれないタイヤの開発競争」へ舞台を移しただけで、いかにSタイヤと呼ばれないまま速く走れるかというタイヤが増えた結果、ジムカーナ競技などではまず「縦溝のないタイヤは禁止」(TOYO R1R規制)、次に「縦溝だけのタイヤも禁止」(クムホV710規制)と進みました。
Sタイヤ規制からSタイヤもどき規制、そして最新はTW280規制
そして最近の流行は、耐摩耗性を表すTW(トレッドウェア)が280以上のタイヤでなければいけない「TW280規制」ですが、エコタイヤは耐摩耗性はあっても構造的にスポーツ性能に耐えうるかどうかはまた別問題のため、あちこちで内面剥離などスポーツ走行時の損傷が課題になっているようです。
結局はまた、「TW280を満たしたSタイヤっぽいスポーツタイヤ」が生まれるだけなのかな、とも思いますし、ストリートであればともかく、スポーツ走行であればSタイヤか、それに準ずるタイヤが必要という状況はずっと続くのでしょう。
筆者はもう年ということなのか、あまり難しいことを考えず、とにかく最新Sタイヤの発売情報を見ては目を輝かせ、ライバルより早く新タイヤに慣れるべく走り込み、すり減ったSタイヤを普段履きしてゴロゴロ言わせていた昔が懐かしいような気もします。